2022.3.7 トークショー 計算と光
一部記録を公開します
森田真生 ( 独立研究者 )
プロフィール千田泰広 ( アーティスト )
プロフィールトークショー「計算と光」
岡部三知代(ギャラリーエークワッド副館長/主任学芸員):
今日はこのような状況の中、たくさんの方にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。
ギャラリーエークワッドは竹中工務店の財団の一つとして「建築・愉しむ」をコンセプトに、生活から建築を見る、という視点から、暮らしの周りに広がる様々な事象と建築やアートを結び、展覧会を通じて、多くの方々と出会う場を提供しております。
光を扱う作品は今回が初めての試みでして、大変緊張いたしましたけれども、作品制作にいたる千田さんのご尽力のもと、見事に漆黒の空間ができあがりました。千田さんの作品こそ映像や写真ではなく、実体験でしか味わえない情感を感じていただけることと思います。本日のレクチャーもここにご参加の皆さんと、お二人のトークとの出会いの場ですので、ぜひこのライブ感を味わっていただきたいと思います。
それでは、とてもワクワクするタイトルですが、トークショー「計算と光」を始めたいと思います。本日のプログラムですが、最初に森田さんからプレゼンテーションをしていただきまして、その後二人の対談に移りたいと思います。それではどうぞよろしくお願いしたします。
[以下、トークショーの内容の一部を編集してお届けします]

森田真生 講演
森田真生(独立研究者):
今ご紹介にあった通り、僕は今京都に住んでいまして、今朝も京都から来ました。僕は今まで不勉強で千田さんの作品のことを知らなかったのですが、今回の企画にあたって岡部さんからご連絡をいただき、まず千田さんがウェブサイトに書かれている文章を読んで、ぜひ千田さんとお会いしてみたいと思いました。特に、光とともに制作するというあり方に興味を持ちましたが、実は作品を見させていただくのは今日が初めてで、まだ作品も見たことがなく、ご本人にも会ったことがない段階でトークライブの準備をするということで、この二ヶ月ぐらい光のことを色々自分なりに考えてきました。ですので、「光」というテーマでこれまで考えてみたことをまずは冒頭にお話しさせていただき、その後、千田さんとの対談に繋げられたらなと思っています。
計算と光
昨年僕は『計算する生命』という本を出したのですが、そこで人間による計算の歴史を古代にまで遡って考察しました。遠い過去までさかのぼっていくと、最初は、粘土や小石を並べるみたいなところから計算の歴史は始まっているんですね。
なぜ粘土を使って昔の人たちは物を数えたり計算したりしたかというと、人間の頭の中では数量がすぐ混ざっちゃうからです。この部屋をパッと見て何人いるか分かる人はいないと思います。この部屋の中に何人いるか知ろうとしたら、数えるという手続きを経る必要があります。つまり、「数字」や「数える」といった道具や技術を媒介することで、この部屋には43人いる、みたいなことが初めて分かるわけです。
1個のものが1個だとか、2個のものが2個だというのは、僕たちは生得的に分かるようにできているのですが、43個のものが43個だというのは最初から分かるようには出来ていないんです。そういう意味では、脳みそは数を扱うことが苦手で、42と43を脳はほとんど一緒くたにしてしまう。ところが、粘土みたいなものを並べておくと、42個と43個の区別をつけて、しかもそれを保存していくことができる。
そうやって初期の頃に人間が少しずつ認識の力を拡張しようとした時には、粘土や小石のようなものの力を借りてやっていたんですね。
これはすごく単純な例ですけど、人間が自分たちでだけでやっているつもりになっていることも、多くの場合は人間より古いものの助けを借りています。よく考えると古くからあるものは古くからいる大先輩なわけですから、僕たち自身は持っていない様々な力を持っていることさえ少なくはありません。
そもそも、宇宙そのものの創造性というのは、人間の創造性と比べるべくもなくて、人間はたしかにクリエイティブな動物かもしれないですけど、細胞より小さかった時空から何千億もの銀河を生み出すみたいなことは人間には到底できない。凄まじい創造力をこの宇宙は持っている。
光に関して言えば、光というのは無駄なくまっすぐ進みますね。人間が何かあるところからどこかに行くために、無駄なくまっすぐな経路を進もうとしたら、頭を使って考えて、最初の一歩をどういう風に進むと無駄のない最短経路になるだろうかということを思考して計算してから動く必要があるわけですが、光はまるでその「判断」を瞬時に行っているかのように、まったく無駄のない経路を進んでいく。
そういう風に自然界ができているんだということで、特に光が偉いわけでもないと考えることもできるかもしれませんが、人間であれば自分で計算して一生懸命考えないと答えが出ないような問題に対して、光は瞬時に答えを出していると見ることもできる。
人間に先立って存在しているものたちが発揮している、知性のようなものには驚くべきものがある。解剖学者の養老孟司先生はよく、木が風に揺れているとか、水が川を流れているとか、そういう自然の何気ないふるまいは、「問題に対する答え」なんだっていう言い方をしています。この地上で太陽の光を少しでもうまく集め、大地から水や養分を吸収していこうという、とても難しい問題をよりよく解こうとして、木はいまある姿に進化してきたわけです。光を効率的に集めたいけれど、集めすぎて葉が傷んでもいけない。ちょうどいい具合に光を集めていくには、どのような形の葉をつけ、どのような葉の色になり、どのように枝を伸ばしていくのがいいのか。非常に難しい問題を、何億年もかけて解いた答えが、いまある木の姿です。だから山の中に入って周りの風景を見渡すと、周りの風景の中には難しい問題を長年かけて解いてきた答えがたくさんある。自然のなかを歩くことは、そういう「答え」に触れていくことだと養老先生はおっしゃるんですね。
そう考えていくと、古くからあるものは、僕たちに比べて単純だとか未熟だとかは必ずしも言えなくて、人間が持っている知恵とは違う種類の知性のようなものを体現している場合が多々あるんじゃないでしょうか。
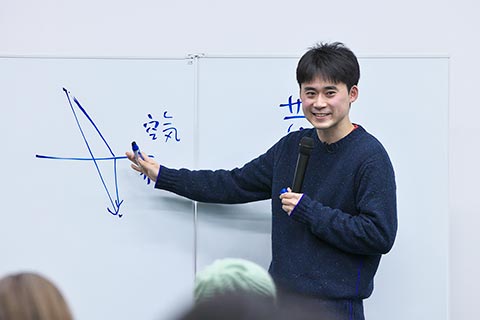
光が世界を作り変える
そういう自然の知性にアクセスするためには、僕たちは感覚を開いていく必要があります。僕たちは実際、様々な感覚を持っています。香りを感じることができたり、音を聞くことができたり、あるいは目を開くとものが見えるという不思議な力を持っています。
生命というのはいつ誕生したかわかりませんが、大昔に生命が誕生してから、かなり最近になるまで、生命は「眼」を持ちませんでした。眼というのは、ただ光を感知するだけでなく、光を利用して物体を識別するための「映像」を形成する器官です。5億4300万年前に、カンブリア爆発と呼ばれる進化の大爆発が起こったと言われていますが、『眼の誕生』(*1)という本によれば、眼はこのカンブリア紀の最初期に誕生したのだそうです。
光はただエネルギーを運んでいるだけではなくて、生命にとって大切な「情報」を運んでいます。
光が運んでくれている情報を生命が利用できるようになったのが「眼の誕生」でした。光は様々な物体に反射して跳ね返る時に、その物体の表面の情報を僕たちの眼に届けてくれます。それを脳が処理して理解しようとするわけです。眼が誕生した当初から、自分を食べようとする天敵とか、自分が食べたい餌とか、そういったものの表面の特徴を的確に捉えることがまずは重要だったでしょう。光があまねく海の中まで降り注いでいますので、沢山の有用な情報を運んでいる。眼がそれをキャッチできるようになったわけですね。
人間ももちろん視覚を持っていますが、僕たちの視覚は「色」の経験も生み出します。特に、人間の色覚にとって重要な意味を持つのは、人間の肌の色です。マーク・チャンギージーという理論神経科学者は、人間の色覚は肌色からの変化と差異を識別するために進化してきたのではないか、と主張しています(*2)。
実は黒人と白人の肌の色は、物理的にはかなり似ているんですね。どういう波長の光がどれくらいありますかというのを比べてみると、人間の肌は、自然界の他の様々なものと比較したら、ほとんどそっくりと言っていいくらい似ている。それが僕たちにとって違って見えるのは、そもそも人間の色覚が肌の色の繊細な違いを検知するために調整されているからなのかもしれません。
実際、肌の色の差異や変化は、感情や健康状態と密接に結びついていますから、これを正確に読み取ることはとても重要です。緊張しているのか、体調が悪いのか。子育てをする時にも、肌色の変化を読み取ることは大事です。
肌の色は基本的に二つの変数によって変化します。一つは肌の下の血液の量で、もう一つは、肌の下を流れる血液の酸素飽和度です。血液がどれくらいの酸素を運んでいるかという血中酸素飽和度は、コロナの重症化の度合いを判断するときにも大切な指標ですが、これを計るために使われるパルスオキシメータも、実は肌の色を見ているそうです。血中の酸素飽和度が高いと肌は赤っぽくなり、低いと緑がかった色になる。また、血の量が多くなると肌は青くなり、少ないと黄色っぽくなります。
そうやって、肌の色がまるでカラーディスプレイのように、皮膚の下の血液の状態を教えてくれるので、人間は眼でよく見るだけで、目の前の人が緊張しているのか、怒っているのか、あるいは元気なのか、ちょっと調子が悪いのか、といった感情や健康状態の変化を、繊細に見分けることができるんですね。
視覚というのはとても面白くて、環境から光が運んでくれている情報を僕たちなりに、情報処理して映像を立ち上げているわけです。その際、映像を立ち上げていくアルゴリズムは、特定の目的に沿ってチューニングされていますので、僕たちは「あるがままの世界」を見ているわけではなく、特殊なメガネを通してものを見ていることになります。そういうメガネを通して、僕たちは緑の青々とした様子や夕日の移ろい、川のせせらぎが反射する光の動きに感動したり、心動かされたりしているわけです。
光はまずエネルギーとして地球に降り注いでいて、大地の形や地球の環境を作り変えてきた。と同時に、光は情報を運び、僕たちの心を形作り、また作り変えてきた。
だから僕たちは光を見ると、まず心が動く。今日の作品でも、暗くなった後にわぁって明るくなってくると、それだけで日が昇ってきたとか、暗闇から抜けて少し視界が開けたような、ホッとすると同時に、ちょっとワクワクした気持ちが動き出すのを感じました。光というのはダイレクトに僕たちの心とつながっていて、だからこそ、僕たちは光の動きや変化に合わせていくようにして、自分たちの思考や感覚を調整し、磨いてきたと言えるのではないでしょうか。
アンドリュー・パーカー『眼の誕生』渡辺政隆・今西康子訳、草思社(2006)
マーク・チャンギージー『ヒトの目、驚異の進化 視覚革命が文明を生んだ』柴田裕之訳、早川書房(2020)
0.1秒先を見る
視覚に関してもう一つ重要なのは、光が眼に届いてから「見える」までには、脳内で情報処理をしているので、何かが見えた時には、見えているものはすでに過去になってしまっているということです。
情報処理にかかる時間は見るものによってもいろいろ違うみたいですが、ごく大雑把に言うと、およそ0.1秒ぐらい、映像を作り出すための情報処理に時間がかかるそうです。つまり、いま見えてると思っているものも、本当は0.1秒前の世界なんですね。このタイムラグは原理的にどうしても生じてしまいます。
しかしこれだと困る。視覚と現実が0.1秒もズレてしまうと、動いているものを掴んだり、何かを避けたりするときに、この遅れが致命的になる。他の感覚と比べても、視覚は特にわずかな時間のズレが大きな問題になります。
そこで僕たちは実際にはどうしているかというと、あらかじめ脳が未来を予想しちゃうんですね。0.1秒の不可避の遅れを埋め合わせるために、脳が0.1秒先を予測して、その予測した未来を見ることにするんです。こうして僕たちの脳は、視覚が必然的に背負うタイムラグを乗り越えるべく、たえず未来を予測している。
視覚は、未来を見ることによってしか現在が見られないという矛盾を背負っているから、僕たちは未来を現在と思って見るようになった。こうした視覚のメカニズムは、僕たちの心の働きにも大きな影響を与えているのではないでしょうか。
今コンピューターを使って僕たちは、もっと遠い未来、もっと遠い未来をと、一生懸命未来を見ようとしています。地球温暖化がどういうふうに進んでいくのか、それに対して的確に行動しようとすると0.1秒先どころか、100年先のことすらなるべく正確に予測する必要が出てくる。遠い未来を予測しないと現在に間に合わないのです。そうしてますます、僕たちの知覚は未来にはみ出していく。
光というのはただただこの地球上に降り注ぎ、僕たちはそれを受動的に受け取ってきただけじゃなくて、生命はこれをエネルギーや情報として巧みに利用してきました。生命と光との長い時間にわたる協働によって、地球環境が作り変えられ、また心の構造が形づくられてきた。僕たちは光とコラボレーションしながら、いまある現実を編んできたのです。
光に応える
そろそろ時間なので、千田さんとの対談に移って行こうと思います。
千田さんの作品を今日拝見させていただいてまず感じたことは、光から何かを受け取ってそれに応えてという、千田さんの制作の過程がすごく双方向的だということですね。
今回展示されている「Myrkviðr」も、光を反射する糸はもう動かないわけですよね。光源だけが動いていて、糸はもう動かない。
ですから、ある種スタティックな構造のようでもあるのだけど、僕はそれを見ていてなぜか、糸の配置を一つ一つ作っていかれた千田さんの身体をすごく感じたんです。光とコミュニケーションしながら糸の配置を決めていくプロセスは、山を登っていくとか、地面に触れながら歩き続けていくとか、環境を感じて応えていくということに似ているのかなと感じました。だから、あの作品を見たときに、スタティックな構造物というよりも、すごくダイナミックなプロセスが表現されているというふうに感じたんです。千田さんの作品は、動き続けながら作られているんですよね。
先ほど初めてお会いしてお話をさせていただいた時も、話し始めたらどんどんですね、お互いの言葉を作りあって進んでいく感じがとても心地よかったんです。受け取ったものに応えていくとどっちが作ったわけでもない制作物が生み出されていく感じというのは、千田さんはいつもそれを光とともにしているのだと思いますが、人間同士でするのも楽しいですね。
今回の展示は、情報を運んでくる光に対して心が応えるというところに基盤があるように僕は思いました。エネルギーとしての光ではなくて、情報を運んでくる光に対して僕たちの心はつい反応してしまう。
「0.04」という作品では、水滴が落ちるという僕たちが当たり前のように知っているはずの現象を、僕たちの通常の視覚のアルゴリズムとは別の仕方で提示することで、同じ現象が思ってもみなかった情報を運んでいたことに気付かされる。
この宇宙は僕たちが思ってもみなかった情報を今も表現しているんだと思うんですね。肌の色を知覚したりとか、森の中で敵から逃げたりするために獲得してきた感覚で僕たちは世界を見ちゃっているので、その感覚からこぼれ落ちているもの、見落としているものがたくさんある。人間は森の中で敵から逃げる、生存するためだけに生きているのかといったら、たぶんそうじゃなくて、この138億年もかけて進化してきた宇宙が表現しているものの、最も素晴らしい所にアクセスするということはすごく大きな目標じゃないかと思います。
で、そのためには森の中で敵から逃げるような知覚だけではなくて、その知覚を少し変容させて組み替えて、宇宙が表現したのに僕たちが見落としている様々なことに気づくことができるような、新しい感覚を開花させていく必要があるんじゃないかなと思うんです。千田さんはまさに、日々そういうことをされているのだと、今回の作品を拝見してすごく感じました。未知の感覚を開くことができた時に、宇宙が表現していたのにまだ受け取ることができていなかった場所への扉が開かれて、新しい世界が立ち上がってくる。千田さんはそういう扉を開こうとされているんだと思います。
